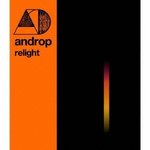2011年10月28日
2011年10月24日
2011年10月21日
2011年10月19日
2011年10月16日
2011年10月11日
2011年10月08日
2011年10月05日
2011年10月02日
2011年09月30日
2011年10月28日
閑話休題:14歳の誕生日
2011年10月24日
閑話休題:ハタチの誕生日
長女が先日、ハタチの誕生日を迎えた。
本人が「グランマや叔父ちゃまやみんな呼びたい!」と言うので、声を掛けた。
弟家族も入れて、12人が集まった。
当日の午前0時過ぎ、なんか感慨があるかと思ったが、さしてはなく、「まあ自分がハタチになったときも、何も想わなかったしなあ」と。
すでにひとり暮らしをしていて、かつ、大学生という中途半端なハタチだった。
面白いことにその日は、中2三女の校内合唱大会の日でもあった。
数ヶ月、もくもくと練習してきた伴奏の腕を見せるとき!
学年優勝はできなかったが、本人としての出来は良かった様子。でもそれで素直に喜べないのが彼女のいいところ。勝てなかったのは、相当悔しかったみたい。
さて、夜の大誕生会。
まずは友人からもらったマグナム瓶のシャンパンで乾杯。
子どもは外して、長女を入れた大人だけで(笑)
ケーキやその他のイベントのあと、私はリビングで弟や義弟、甥たちとビデオ(MotoGPとか)を見ていた。
そうしたら長女がダイニングの方へ来いという。
何かと思ったら「お父さんたちにプレゼント」「親になった20周年記念だよ」だってさ。
なんとも洒落たことをする子だこと。
お茶碗とお箸セット。
大切に使わせていただきましょう。
その後、みんなで三女の合唱コンのビデオ鑑賞。
長女が必死で撮ったもの。
伴奏も上手だったし、歌うときは声もよく出ていた。本人が恥ずかしがるくらい。
その日の主役の座を奪われてちょっと拗ねていた三女の機嫌も直りましたとさ(笑)
2011年10月21日
2011年10月19日
Steve Jobsに捧ぐ ~学びの源泉とダイヤモンド・オンライン
2011.10.14に「学びの源泉」で『プレゼンテーション・クロージング(Jobsに捧ぐ)』をリリースしました。
2011年10月16日
JA共済研修@海浜幕張 「次は自分が講師の気迫!」
2011年10月11日
音楽日記:2011秋 androp、SEKAI NO OWARI、サカナクション
2011年10月08日
11月の新刊タイトル決定。『一瞬で大切なことを伝える技術』!
昨日、かんき出版内で会議があり、私の11月の新刊タイトルが決まりました。
2011年10月05日
10/3アカデミーヒルズでライブラリートーク!
2011年10月02日
9/21長岡市 旭岡中にて!~地域保護者・教員講演編
2011年09月30日
お手伝い日記:夜中に娘たちをたたき起こすの巻
夜中、次女、三女がちゃんと家事をやっていないとの報告を受ける。
2人とも事情は違うが、ここ1~3ヶ月、まったくもって不十分な状況。
もちろんこれではダメである。
しばらく考えたが、
・私が直接言う
・ちゃんとできないなら高校も大学も行かせないと伝える
ことにする。
2人とも寝ているので、翌朝、とも思ったが、学校に行く前にそれでは気分が悪いだろうなあとも思い、たたき起こすことにする。
床についたばかりの三女はすぐ起きたが、次女は深く眠っていてなかなか起きない。
でも枕をぽんぽん蹴って起こす。
「座って」と言って、正座させる。
まずはお手伝いの状況を自己申告させる。
2人ともちゃんとやっていないと言う。
理由も聞くけど、大したものはないという。「それではダメ」
各自、何をやるのか、を確認して、明日からちゃんとやるよう厳命する。淡々と。
まずは翌朝、それを各自、お母さんに伝えるように、とも。
数分で終了。
夜中、次女は「お父さんに怒られた」と泣きながら、母親に報告したらしい。
三女からは今朝、何も報告はなかったらしい・・・。
まだまだ戦いは続くのであった。