カテゴリー: 11 一般的考察
2011年04月14日
2011年04月09日
2011年04月07日
2011年02月17日
2011年01月25日
2010年12月31日
2010年12月07日
2010年11月27日
2010年11月21日
2010年06月29日
カテゴリー: 11 一般的考察
2011年04月14日
『正しく決める力』と柳家小三治
2011年04月09日
反自粛戦線を! その二~分業の力
2011年04月07日
反自粛戦線を! その一~空気と戦う
2011年02月17日
月と星:良い目を持つと いうこと
プリンターのインクが切れたので、高島屋SCに夕方、買い物に行った。
帰りに交差点で出会った、ベビーカー母子。
子どもは2歳くらいかなあ。
信号待ちの間に、その子が突然大きな声を上げた。
そぷかあ、この家でも「月を最初に見つける競争」をやっているのね。
いいことだ。 うんうん。
などと思っていたら、間髪入れず今度は
えっ、星も出ていた?
いや、出ているに決まっているのだけれど、明るい交差点で、そこまでははっきり見えない。
ちらりと横目でその子の顔の方向を確かめて、見てみれば確かにそこに星が。
うーっむ、あれを見つけるとは・・・。
そこですかさずその女の子が叫ぶ。
これまた自分ではすぐに見つけられず、彼女の顔の方向で何とか見つける。
参りました。
ホントに目の良い子。
きっとその目が、あなたに色々な人生の幸福をもたらしてくれるよ。
2011年01月25日
1/25 日韓対決。続けることの価値を細貝と本田圭佑に見た!
本田圭佑はやはりすごかった。すばらしいパス、センスとスピード。
1-1で迎えた延長前半7分、彼のスルーパスに反応した岡崎が韓国ディフェンスのファールを誘い、PKを得た。
もちろんキッカーは、本田。
しかし彼の真ん中目を狙ったシュートはミスとなり、(向かって)左に飛んだキーパーの足に当たる。
ボールが跳ね返って転がるけれど、本田のフォローは間に合わない。
そのとき、もの凄いスピードで現れ、左脚一閃、ゴールを決めたのが細貝。
香川に代わって87分に投入された途中出場の彼は、長い助走をつけて、本田がシュートを放つとともに、ペナルティエリア内に突入していたのだ。
でもそれは偶然でもセンスでも思いつきでもなかった。
PK戦を制したあとのインタビューで、彼は言った。
「個人的にもこぼれ球はしっかり狙っていた」
「昔からPKのときには必ず狙うようにしている」
と。その何年にもわたる積み重ねがあったから、あの絶妙の突入ができたのだろう。
そしてその何百回の繰り返しの果てに、代表戦のPKで自分の前に玉が来るという機会を得たのだろう。
「(アップのために)一度もイスに座ることなく、ずっと動き続けていた」
「スタメンで出ることがないとなれば、途中から出るしかないので、与えられた時間で与えられた役割をしっかり果たそうと思っていた」
人事を尽くすものにのみ、天命は訪れる。
本田は延長戦後の、PK戦で先鋒をつとめ、渾身のシュートでチームに勢いをつけた。
この意地と気合いもまた、本田圭佑を本田たらしめてきた、「継続」であろう。
これでこそプロ。これでこそ日本代表。
あー、楽しかった。次も、応援しようっと。
2010年12月31日
ふりかえらない
みなの日記を見て、思った。
いや、昔あったのかもしれないが、忘れて思い出せない。
かつ、最近は少なくとも振り返ったことがない。
忘れっぽいのもあるが、そもそもプランがないから、振り返っても(チェック)意味がないのだろう。
本とかでも「PDCA」は重要、とか書いているのにヒドイ話である。
日常生活においてのPDCAは、でも、かなりやっているほうだろう。
だめなことはすぐに直す。それは即時に行われる。
しかし、年間計画や中期計画を立てないから、大きな振り返りが、ない。
反省はあるが、後悔はない。
機会はとるが、計画はない。
今は見つめるが、過去は見ない。
ただ、走り続けるだけ。
来年も、また。
2010年12月07日
富士ゼロックスでセッション
10名あまりのナレッジワーカーによる、セッションが行われた。
2010年11月27日
The innovations from weak ties
2010年11月21日
最密充填構造
2010年06月29日
MUJIの誕生と崩壊と再生と
まずはこちらの記事から。
『ハカる考動学』でも実例を紹介しているが、実は、『crmマーケティング戦略』でも取り上げている。
もちろん、もともと西友の一ブランドだった頃から知っていて、その栄枯盛衰を見てきた。
英語のNon-branded goods(ノーブランド品)を、無印良品、と「直訳」したセンス。
わけ あって、安い。いう秀逸なるコンセプト。
でも成功するにつれ、店舗は多様化しチェーン展開の基本である統一的オペレーションを無視した。
ブランドとしての既存への反抗心が、一律の運営を拒んだのかも知れない。
低価格をうたうことは出来なくなるなかで、その存在意義も無くなっていった。
本当は、凄い力を持っているのに。
2001年、社長についた松井忠三氏は、店舗フォーマットを統一し、マニュアルを整備し、ブランドコンセプトを明確にした。
それはすなわち、既存の企画に合わない店舗を閉鎖し、新規事業から撤退し、不良在庫を焼き、商品を絞り込む、「捨てる」作業だっただろう。
そして無印良品は、復活した。
その後、良品計画がネットで始めた「共創型商品開発」は、そのさらなる進化の現れだった。
顧客を巻き込み、その智恵をうまく借りて、良い商品を効率よく世の中に出していく。
日用品で、そして、住宅で!


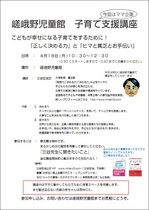


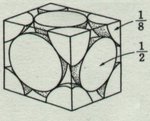

-thumb-80x101-1048.jpg)

