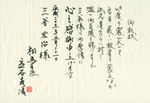2011年06月08日
2011年06月06日
2011年06月03日
2011年06月01日
2011年05月29日
2011年05月28日
2011年05月26日
2011年05月25日
2011年05月23日
2011年05月20日
2011年06月08日
カメラを写真撮影機と呼ばせるお国柄:フランス
2011年06月06日
戦略ゲーム
2011年06月03日
政局ゲーム・・・星0個
「民主 小沢氏ら15人処分先送り」というニュースが流れた。
(参院がダメだから意味ないけど)衆院での絶対安定多数には問題ないから、15人くらい除籍すれば良い。
とはいかんのだろうが、まったくもって中途半端。
まあ、「時期を明言しない辞意表明」でひっくり返るくらいだから、小沢・鳩山同盟もその程度の覚悟だったと言うこと。
そりゃそうだ、本気で造反して離党したら最も価値なくなるのはこのお二人。
それにしても、改めて思う。鳩山由紀夫とは不可解な人だ。
首相としてはただ沖縄と日米関係を混乱に陥れただけ。
金がらみで退陣する際には盟友小沢シを道連れにし、
菅シが総理になると反菅に回って小沢シと蜜月。
そしてまた勝手に菅シと手打ちして・・・。
なんのポリシーも深謀も見えない。
民主党よ、はよ仕事せんかいな。
自民党だって、今回の危機の大部分を作りだしたのは、自分たちの政権時代だったという反省を深くしつつ、行動してもらいたい。
谷垣シも何を期待しとるんかいな。棚からぼた餅とか考えてないで、ちゃんと国を動かさんかいな!
(初稿では一部不穏当な表現があったので、ちょっと修正。でも氏とか言う気にならないのでシに)
2011年06月01日
1100人を超える震災遺児・孤児たちのために、できること
2011年05月29日
新潟県立加茂高校で授業とPTA講演
2011年05月28日
特別講義ルークの冒険@佐賀県武雄市6/15.16開催!
さて、行きますよ、武雄市。
あの温泉と市長さんで有名な、佐賀県武雄市!
Z会の寺西さんの紹介〔宣伝〕で、市役所から申し込みが来たのが3月。
そして震災のバタバタで途絶えていたが、先週、6/15.16開催と決まった。
・6/15 12:00~ 若木小学校 56年
・6/16 09:35~ 東川登小学校 56年
11:35~ 西川登小学校 456年
田舎の学校、大好き。
無理を言って60分授業を確保していただいた。
60分で何ができるか、もう一回、考え直して構成してみた。
あとはその場の対応力勝負だ。
あ、でもまだ準備出来ることがひとつ。
2011年05月26日
特別講義ルークの冒険@KTC高等学校 名古屋校!
2011年05月25日
執筆日記P6:いよいよデザイン!
2011年05月23日
15家族以上が必要だった。現人類の東進物語
2011年05月20日