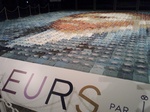2010年05月27日
2010年05月25日
2010年05月24日
2010年05月24日
2010年05月22日
2010年05月19日
2010年05月17日
2010年05月15日
2010年05月14日
2010年05月13日
2010年05月27日
御料牧場、SO206、Lights
左
皇居内にある宮内庁でお呼ばれ。おいしかった。
バター香が強いが、飲み味はすっきり。
中
DocomoのSony製 携帯電話。1998年。
私が昔、愛用していた機種。
デザインも良かったが、左上のジョグダイヤルは、もの凄く便利だった。
右
ISL@永田町にある光たち。
昨晩は、1830から2340までノンストップで議論。
夏、50余名の高校生たちと会うのが楽しみだ。
2010年05月25日
本とバイクと男の子
2010年05月24日
AKKのススメ?
『20代で伸びる人、沈む人』と言う本の紹介記事があった。
空気を読めても、その上のレベルで行動できるヒトがAKY。→伸びる。
空気を本気で読めず(読まず?)ハマルのがHKY。→沈む。
まあそれは、いい。
でも、ほとんどの人間はそこにはいない。
でもそこから一歩進むには、どうすればいいだろう。
もうちょっと考えてみよう。
2010年05月24日
『ハカる考動学』の書評ブログたち
2010年05月22日
次女の毒舌と勉強と運動会
高2の次女は昔から結構、毒舌である。
まあ、ともかく、彼女独自の観察眼と、価値観に基づいた、一刀両断的意見なわけだ。
それが学校の愚痴とともに、一杯出てくる。
彼女にすれば「ストレス解消!」の手段でもあるらしく、言った後はすっきりランラン、である。
まあ、いいかあ。
学習カードなるものがあって、生徒が1週間の自宅学習時間を先生に報告し、先生がコメントを返してくれる。
次女の先週の実績は、
・平日平均1時間/日、週末2時間/日。週合計8.5時間
これはその学習カード上部に大書されている、
・MARCH合格者の最低ライン、平日1時間50分、休日3時間3分
のほぼ半分である。
さらに
・都立進学校では 平日3時間、休日5時間
とも書いてある。その1/3である。
この自己申告分の他にもちょこちょこやっているという目撃報告もあるが、いずれにせよ短いことには変わりはない。
ではその他の時間何をやっているのかというと
・家族とのおしゃべり(毒舌)
・マンガ
・ゲーム(今はキングダム・オブ・ハーツ)
・睡眠
である。特に睡眠は外せない。22時には寝ているので、夜は結構忙しいのである。
週末も、特に友だちと出かけるでなく、イエでゴロゴロしている。それが幸せなそうである。
このマイペースは小学校の頃から変わらない。
高校になってひとつだけ違うのは、クラスで文武両道として注目されている、ということだろうか。
火曜日には運動会がある。
馬になったクラスメイトたちを踏んづけて走る役なそうだ。
落ちたら終り。なのにクラスメイトたちは「楽勝」と太鼓判。
そのプレッシャーですでに気持ちが悪い、小心者でもある。
文武両道、カッコいいじゃない。
マイペースでガンバって。
2010年05月19日
5/19 新渡戸文化小学校 アフタースクール授業
2010年05月17日
6月新刊にまつわる2つのウソ…
2010年05月15日
三女の涙:メガネ編
うちの三女は目が悪い。
これまでは弱い遠視で、ここ最近、近視が進んだ。
メガネを買い直すために、先週、渋谷マークシティにあるzoffに行き、お気に入りのものを選んだ。
もともと近所のメガネスーパーでは気に入ったものが無く、かつ、値段が高かったのでお気に入りのzoffに。
そこでスキなデザインのものを見つけたのだったが、9000円した。zoffでは高いラインだ。
今までのが5000円。
今のフレームを流用できないのか?とかで、すぐには買って貰えずペンディング。
そこでまず私が三女に提起したのは
・zoffだけでなく、他の店も調べること
ところが、ネットで調べただけで「他にも良いのはない」とメールしてきたので、再び
・実際にお店に行って確かめなさい
・zoffは原宿駅前に本店がある。あなたがネットで調べたJINSもその近くにお店がある。その2つの店を調べた上で、決めなさい
・そうするなら9000円までは出してあげる
本人、部屋で泣いている。
おそらくは「お店回りは面倒くさい」「おねえちゃん(次女)はそんなこと言われなかったのに」ということで。
後者は勘違いだが、前者は、ま、仕方ないね。
がんばんな~
2010年05月14日
5/19 新渡戸文化学園 小学校でワークショップ
5/19午後は、理事をやっている「放課後NPO アフタースクール」のお手伝い。
新渡戸文化学園は歴史ある学校だ。
2008年、80年間親しんだ東京文化学園から名前を変え、小学校は杉並区和田から中野区の本校に移転した。
その保護者会に合わせての、子ども向けイベント、である。
まあ、お子さま預かりサービス、でもある。
4~6年生数十名向けに90分の授業をやる。(1330~)
テーマは「イロの不思議・カタチの不思議」としているが、さてさて。
カタチの不思議の小学生版を、もう一回、考え直そうかな。
特にコップや紙コップは、流石にそのままでは難しい。
思案のしどころである。
例えば
ことで、4~6年生にも楽しめるものになるのでは、ないかなぁ。
2010年05月13日
慶應MCC 夕学五十講 w/ ゴッホとサイン会
夕学五十講、2001年から続いていると言うことを、初めて知った。
今年が10年目だから、誰が1000講目になるのだろうか。(初年度は75講やったらしい)
さて、今日は丸ビルに30分前には到着。
これを見ながら透明エレベーターに乗って会場である7階へ。
日本中のサテライトに飛ばすこともあって、そちらとの画面設定が上手く行かず、直前までばたばたと。
それも無事終わり、1830からスタート。
出だし、「イロの不思議」で、あまりにもみなさん真剣に(かつ静寂の下に)取り組んでいるので、ちょっと心配になる。
これは発想力の講義。黙ってじっとしていても、ダメよ。
後半、グラスのヒミツに入って、チームディスカッションをやると、流石にみな沸いてくる。
がやがや、ざわざわ。
最後の紙コップ演習では、200人による、ざくざく、コンコンも混じって、良い感じに。
そうそう、こうでなくちゃ。
最後は発想力強化法に引っ掛けて、三谷家教育論の一部を(笑)
やはり「ヒマと貧乏」を与えないと。
そしてそれは「自由と制限」の与え方という、人材教育の根本問題でもある。
講義90分が105分に伸び、30分のQ&Aが15分に。
質問は、結構、いいモノだった。
・本の読み方、捨て方
・発想の源、育て方
等々、今日の学びを、自分のものにしようという姿勢が伺えた。
講義後、「サイン会」
かなり恥ずかしいが、本屋さんが来て売っていただいたお陰もあり、25名ほどとお話しすることが出来た。
サインしながら名刺交換と2~3言、言葉を交わす。
それだけでも、みなさんの感じがつかめて良かった。
他にもtwitterで呟かれた、こんな感想も。
・ありがとうございましたー、自分の頭のかたさにちょっと絶望しました!!(爆)
・エクササイズが多く、楽しみながらエッセンスを学べました。(サテライト先より)
さて、次は
・5/15 アカデミーヒルズ「ハカる考動学」の初研修
・5/19 新渡戸文化学園 4~6年生向けワークショップ(?)
だ!